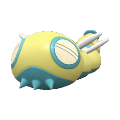Dudunsparceの名前の由来・設定考察
4年前の私「ツチノコを売って生計を立てたい」
?????
Dudunsparce (Two-Segment Form)
Pokemon Scarlet
“This Pokémon uses its hard tail to make its nest by boring holes into bedrock deep underground. The nest can reach lengths of over six miles.”
詳しい内容は “続きを読む” から。
概要
第九世代で登場した、ノココッチです。
ノコッチの追加進化であり、順当に一回り強化した能力をしています。
1/100の確率で胴体が1つ多いみつふしフォルムが存在しており、一種の収集要素になっています。
進化条件にもなっている系統専用技として、「まもる」の効果を無視するハイパードリルを習得しています。
てんのめぐみとへびにらみ、ずつきも健在であり、強化された能力から高確率の怯みを狙うこともできます。
名前の由来
![]() Dudunsparce (Land Snake Pokemon)
Dudunsparce (Land Snake Pokemon)
Dunsparce “ノコッチ” を重複させたものと思われます。
Dunsparce 自体はおそらく dun “陰鬱な色の” + sparse “まばらな” 、dunce “愚か者” だと4年前の私が言っています。
いずれの言語でも、ノコッチの現地名をもとに重複させる、「2」をつけるなどの名称になっています。
ノコッチの節が増えただけのデザインに見えますが、実際はふたふしでも体長2.5倍ほどに巨大化しています。
同じような立場のリキキリンともども、知っているポケモンに見せかけて異常さを感じさせるデザインです。
惜しいのは大穴の野生が初見ではなく、どちらもジムリーダーの手持ちに入っていることでしょうか。
それはそれで道中の新規性を担っているので、難しい選択ではあります。
図鑑説明と設定
“This Pokémon uses its hard tail to make its nest by boring holes into bedrock deep underground. The nest can reach lengths of over six miles.”
“このポケモンは硬い尾を使って地下の岩盤の深さに穴を掘り巣を作る。巣は6マイル以上の長さに達することもある。”
岩盤を穴だらけにする、新しいタイプの危険なポケモンです。
大穴にたくさんいるので、テラパゴスが滅んだ地殻変動の原因なのかもしれません(そんなはずはない)。
全体的にスケールアップしているだけで、生態はほとんど進化前から変わっていません。
ただ、多少臆病さは減っているらしく、巣に迷い込むと案内してくれたり、外敵は攻撃して追い払ったりします。
Dudunsparce (Three-Segment Form)
Pokemon Violet
“A recent study uncovered that the number of segments a Dudunsparce’s body has is determined by the Pokémon’s genes.”
“最近の研究が、ノココッチの体の節の数はそのポケモンの遺伝子によって決まっていることを明らかにした。”
同じ個体は同じフォルムに進化することを教えてくれています。
単純な顕性/潜性の遺伝子であれば、2世代以内にみつふしがいなければ必ずふたふしになるはずです。
そもそも、1/100は明らかに偏りすぎています。
現実的に解釈しようとすると、遺伝的にリスクが決まっている先天性の奇形というのが近い気がします。
ただ、両親の形質によって確率が変わるわけでもないため、遺伝子というのはあまり納得できる説明ではないです。
まあ、全ポケモンの遺伝子を持つミュウなどというのがいるため、遺伝子(ポケモン)は現実の生物とは事情が違うのだと思います。
ちなみに、実際の仕様としてみつふしは一切遺伝性の情報とは異なる乱数で決まっており、事実上完全なランダムです。
遺伝リスクに関しては、『金銀』の色違い(特定の個体値で発現する)がそれと言えます。
さて、今週のポケモンはノココッチでした。
色違いミライドン・コライドンのコードを求めて歩きましたが、どこも終了ですね。
品切れしないであろうポケモンセンターに行くしかないのでしょうか。
それでは、来週もまたよろしくお願いします。